|
1 事業の定義について 洲崎鋳工(株)の概要と「事業の定義」について、洲崎氏から説明 |
|
|
| 昭和4年(1929年)創業。鋳物製造を続ける中、35年前からオートリールの生産を開始。現在に至る。 |
|
本社工場(鋳物工場)・大阪工場(鋳物工場)・精密機械部工場(リール工場)の3つの工場があり、各工場に約20名余の従業員が勤務し、総数75名。 |
|
|
|
1.
組織をとりまく環境(社会とその構造・市場と顧客・技術動向) |
|
社会とその構造
生産設備から社会資本、生活設備重視への転換 |
|
市場と顧客
低価格志向?本質の性能重視 |
|
技術動向 IT、センサ、制御技術、新素材 |
|
|
|
2. 組織の使命 |
|
素材・機械部品のトータルサプライヤー |
|
移動機器へのユーティリティー供給、移動機器との入出力信号交換システムの製造販売 |
|
巻取技術(何を巻き取るか) |
|
|
|
3.
組織の強み(コア・コンピタンス-中核的卓越性) |
|
鋳物の製造技術 |
|
マーケティング-設計-製造-販売-(メンテ) |
|
リールに関するニーズに合わせたR&D、設計、生産、サービスの提供用途開発 |
|
|
|
<洲崎氏の説明を聴いて参加者のディスカッションの内容(鳥井氏のレポートから)>
洲崎鋳工さんは、鋳物業とオートリールという二つの事業に取り組んでおられます。
鋳物産業の現況については、資料がありませんので分かりませんが、洲崎さんのお話では、量的には減っているが昨年までは儲かっていたとのこと。また、オートリールにしても、一見ローテクでどこでもできそうなものですが、意外とよそからの参入はないとのこと。(こんなものが商品になるんだなという驚きの言葉がちらほら)いわゆる成熟産業の中で最後まで、しぶとく生き残るという生き方も中小企業の優れた戦略なのかも知れません。(鋳物に関しては、今や大企業は全く手出しをしない領域になっている。)但し、その戦略はいつまで功を奏すかは一度検証しておくことが必要である。 |
|
現事業にあまりとらわれず、洲崎氏自身で新しい展望を考える時のように思われる。また、事業継承対も必要である。 |
|
参加者の意見として、自分達の売りは何なのか、それもサービス業という考えを基本に考えていくことが大切」(山本さん)「今や人や技術ではない。対応力だ。悪いとことは一度潰してやり直した方が良い」(秋田さん)「勝ち組、負け組がはっきりしてきている。要は元気なtころをつかむことが大切。その際従来の属人的営業ではだめ。戦うものをもち、短いコンセプトでまとめ、ぱーっとやること(不特定多数を相手にする?)」(鈴木さん) |
|
|
|
以上のとおり「事業の定義」について説明とディスカッションがあったが、事業を定義する以前に、洲崎氏自身の「経営理念」(何のために事業を営むのか)が明確になっていないのではないかとの指摘があり、今後、理念の追究を続けるとの回答であった。 |
|
須崎氏自身は3代目になるが、将来の事業継承のためには、相続税が大きな問題になるのではとの指摘もあった。 |
|
|
|
2 新たな顧客創造のための仕組み創りの提案
ディジタル「ものづくり」プラットフォームについて |
|
配布資料「匠の京(みやこ)」(仮想ものづくり都市)に基づき、(株)アクト岡本氏から説明があった。 |
|
<匠の京(みやこ)の概要> -配布資料から- |
|
本システムは、インターネット上に仮想のものづくり都市空間を構築し、その都市空間の中にバザールを形成し商取引を活性化させ、新市場を形成する為のものである。 |
|
少し前までは、インターネットを利用することにより、中小企業の商取引に有効に活用され、遠くは海外との受発注が行えるようになると期待されていたが、現実問題として言語・商習慣の違いに加え、たくさんの情報から目的とする情報にたどり着くまでの煩雑さが目立ち、有効に機能していないと思われる。 |
|
そこで、一つの取組みとして仮想都市空間「City」をインターネット上に構築し、工業団地・集会所・技術サポートセンターなどを出現させ、自由な討論(メーリングリストを見立てる)・技術の展示(ホームページを見立てる)などを行えるようにし、コンテンツの面白さを加味することにより、活性化した都市作りを行えるようにします。 |
|
<未来企業の会メンバーで今回欠席の方へは、メールでご連絡いただけば、配布資料を送付します(ワード97文書のWinZipファイル714K)> |
|
システム概念 |
|
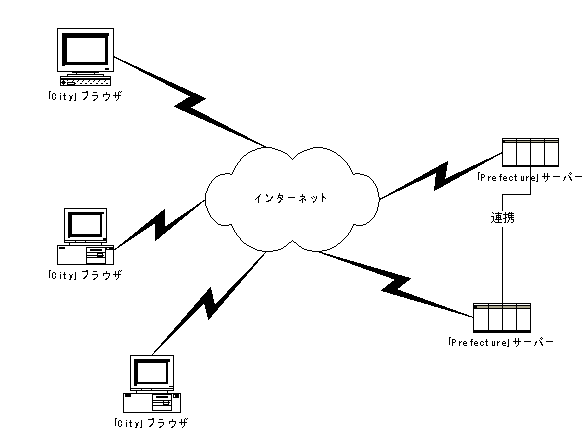 |
|
|
|
「匠の京」初期インターフェイスイメージ図 |
|
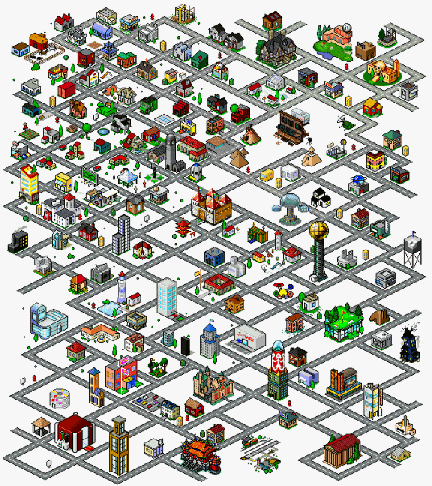
|
|
|
|
伽藍とバザールの概念で、いわゆるバザールをネットワークを活用して形成しようと言うもので、今回の提案は、あくまで議論のための叩き台として作成されたものです。 |
|
今後は、より具体的に何をどうしようとするのかについて、ディスカッションを続けていきたいと思います。 |
|
それぞれの強みを共有して、新たなものを創造するための仕組みと言うようなものなのでしょうか。 |
|
|
|
|